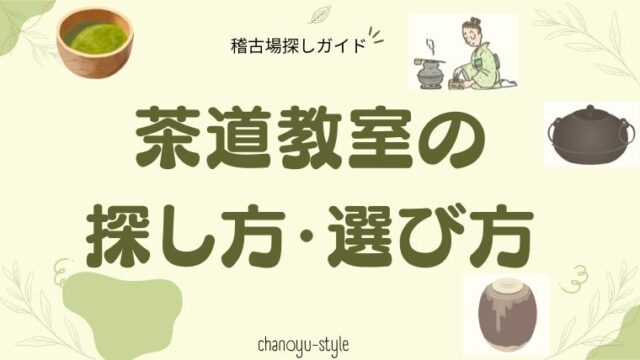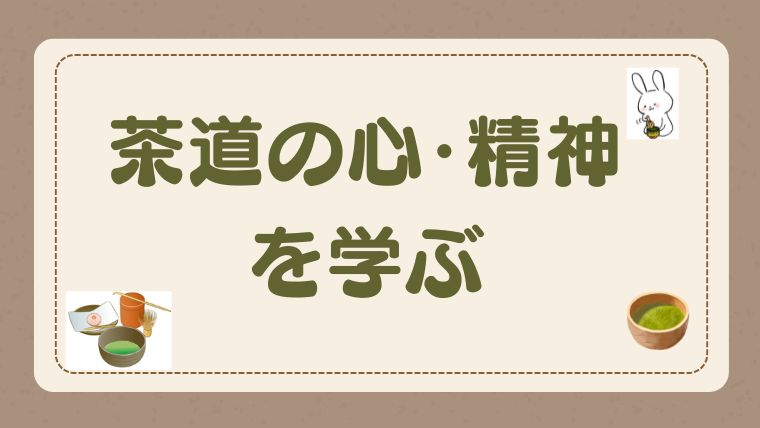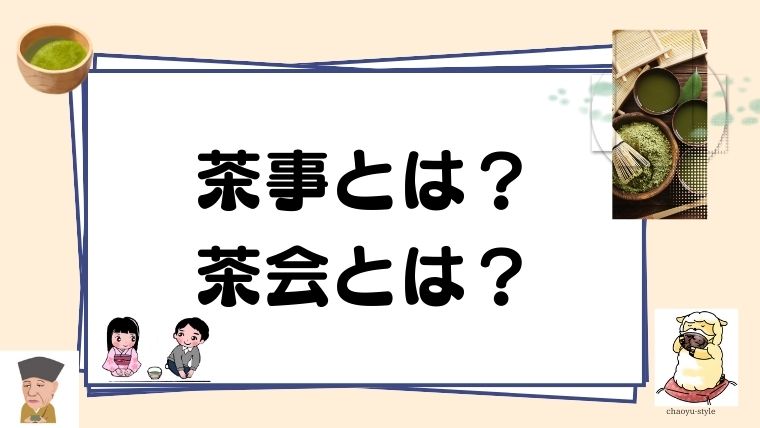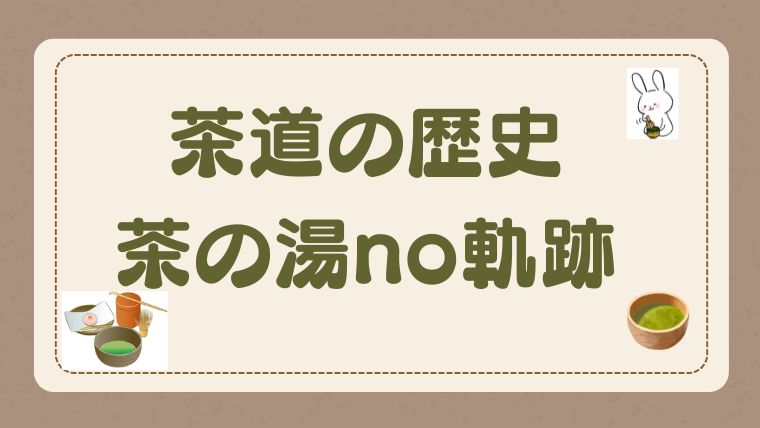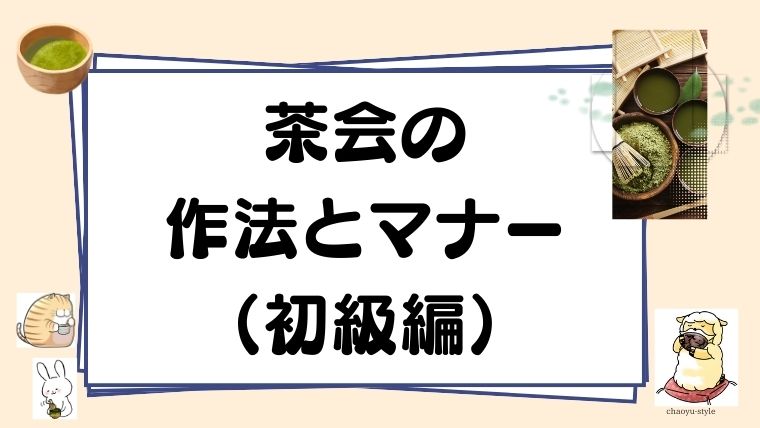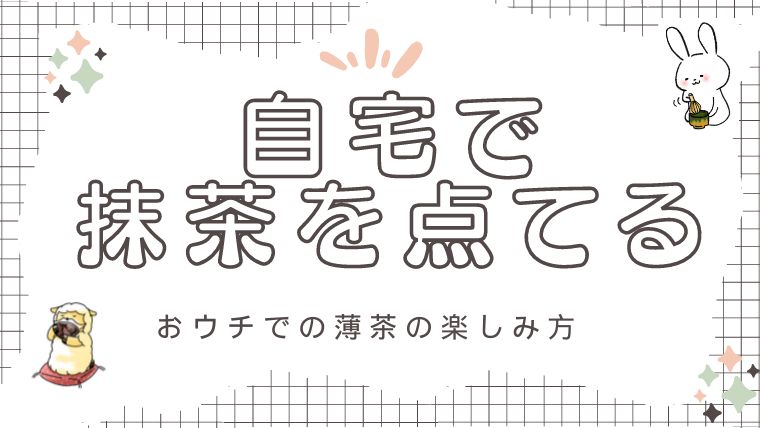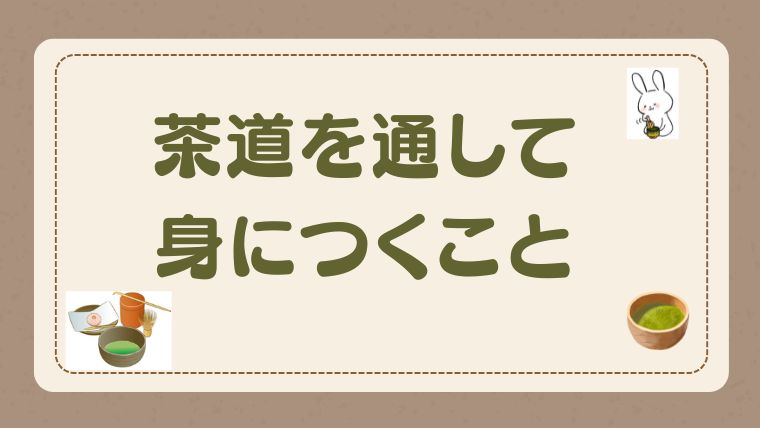茶道のお稽古→初心者が茶道教室で稽古するときの基本作法・所作・マナー
これから茶道を初めてみたい人にとって、茶道のお稽古って何をするの?ということが気になるところでしょう。
そこでここでは、
- お稽古場での茶道稽古の内容
- お稽古の基本作法・マナー
- 初心者が茶道のお稽古するときに気をつけるべきこと
を中心にお話ししたいと思います。

これから茶道を始める人だけでなく、すでにお稽古を始めている人もご参考にしてください。
事前準備:茶道のお稽古場に持参するもの
- 数寄屋袋(すきやぶくろ)
→稽古に必要なものを入れておく袋です。好みのものを揃えましょう。 - 懐紙(懐紙)
→茶菓子を乗せたり、汚れを拭くための和紙です。男性用と女性用があります。 - 黒文字(くろもじ)
→主菓子を食べるときに使います。 - 帛紗(ふくさ)
→茶道具を清めるときに使う布地です。洗わずに古くなったら買い替えます。 - 古帛紗(こぶくさ)
→茶道具の拝見と、濃茶を飲むときに使います。 - 扇子(せんす)
→挨拶するときに使います。結界の代わりとして儀礼的に用います。 - 白い靴下・足袋
→畳を清潔に保つために稽古場では白い靴下に履き替えます。洋服の際は足袋の代わりに白い靴下を履きます。 - 稽古着
→洋服の上から着用する着物を模したものです。
事前準備:身だしなみの作法・マナー
茶道のお稽古では、必ずしも着物を着用する必要はありません。
特に初心者の方や、まだ着物の用意がない方は、洋服でお稽古しても構いません。なお、洋服でお稽古する際には着物に模した「稽古着」を身に纏います。
また、お稽古に相応しい格好をして、心身を引き締めて茶道稽古に臨みます。身だしなみには気をつけましょう。
- 爪は短く切る
→茶道具を傷つけないようにします。 - 指輪、ネックレス、イヤリング、ピアス、腕時計は外す
→茶道具を傷つけないようにします。 - 香水はつけて行かない
→茶室の雰囲気を邪魔しないために、香水はNGです - 服装
→清潔感のある服装を心がけましょう - 髪は束ねる
→髪が長い方は、お辞儀の際などに顔にかからないようにします。
稽古当日:稽古場に到着した際の作法
お稽古当日は、時間に遅れないように早め早めに行動しましょう。
茶道教室についたら、
- 先生への挨拶
- お稽古の準備
をします。
先生には「本日はご指導のほど、よろしくお願いいたします」と丁重にお願いします。
その後、
手早く身支度を整えて(白い靴下を履くなど)、お稽古が始まるのを静粛な心で待ちます。
茶道のお稽古:基本作法
茶道のお稽古では、大きくみて二つのことを稽古します。
「客の稽古」
「点前(てまえ)の稽古」
「客の稽古」では、お茶をいただく際の所作を学びますし、
「点前の稽古」では、お茶を点てる際の所作を学びます。
また、前提として、
その両者において共通するお稽古の基本作法としては、3つ挙げられます。
- お辞儀の作法
- 歩く作法
- 立つ作法
以下において、3つの基本作法について確認しておきましょう。
お辞儀の作法
茶道では、
「真(しん)」 →正式な「深い」お辞儀
「行(ぎょう)」→客同士の「中間の」お辞儀
「草(そう)」 →席中の会話での「浅い」お辞儀
という3種類のお辞儀を、場面により使い分けてお辞儀をします。
茶席で歩く作法
茶席では、「すり足」で歩きます。
すり足とは、
「つま先を畳に擦るイメージで歩く足運び」です。
足の親指に体重を乗せるように意識して歩きます。

畳の上を歩くときは、畳の縁(へり)を踏まないように注意しましょう。
畳の縁を「右足・左足」のいずれかで越えるかに着いても、決まりがあるケースがあるのでいずれ覚えましょう。
茶席で立つ作法
茶席では立ち方の作法があります。
立つ際には、以下の3ステップを意識しましょう。
① 踵(かかと)を上げて跪坐(きざ)の姿になる
② 片足を少し前に出す
③ そのままの姿勢で上に吊り上げられるように立ち上がる

茶席での立ち方は、力を使います。茶道は筋トレ的な要素もあります。
客のお稽古(お茶をいただく所作)
床の間での所作
茶席に入ったら、まずは床の間に向かいます。
床の間には、
「お軸(掛け軸)」と
「茶花」
があるので、拝見しましょう。
お軸に書いてある言葉の意味と、茶花が醸し出す季節感を確認しましょう。

お軸に書いてある文字が分からなくても大丈夫です。先生が詳しく説明してくれるでしょう。
毎回お茶花が異なるので、楽しみになります。
茶菓子をいただく所作
客のお稽古では、茶菓子を食べて、お茶をいただきます。
点前の方がお茶を立ててくれるので、お茶をいただく前に茶菓子を食べることになります。点前の方が「どうぞ」と言ったら茶菓子を食べましょう。

お茶は、茶菓子を食べてからいただきます。
茶菓子の甘味が口の中に残っている間に、薄茶(または濃茶)を飲むと、お茶をとっても美味しくいただけます。
お茶を飲む所作
点前の方がお茶を立ててくれたら、お茶をいただきます。
所作の詳細はまた記載しますが、
- 点前の方と、左右の方に挨拶する
- お茶を押しいただく
- 茶碗を2回回す
- 飲み終わったら「スッ」と音に出す
- 茶碗を縁外に戻して拝見する
このような5ステップがお茶の飲む際の基本所作となります。
点前(てまえ)のお稽古(お茶を点てる所作)
水屋でお稽古の準備
点前のお稽古の準備する場所を「水屋(みずや)」と言います。
点前の稽古には、
「水屋での事前準備」
「点前」
「水屋での後片付け」
が含まれます。これら全てが「点前の稽古」なのです。

水屋にはお稽古で使う茶道具が置いてあります。
水屋の使い方は、所作の美しさとつながる面がありとも言われます。
水屋は清潔な状態を保つように心がけましょう。
点前のお稽古
点前のお稽古では、いろいろな道具を使います。
茶道具の種類は多いですし、使い方の決まりもありますが、
最初は焦ることなく、心を込めて一つ一つの所作を行うようにしましょう。
点前の稽古では、
- お客様に茶菓子を運ぶ
- お抹茶を点てる
ということをします。
お客様に茶菓子を運ぶときには、茶菓子を持つ位置に注意を払いましょう。茶菓子はみぞおちの高さを意識して持つと、綺麗な運び姿に見えます。
お抹茶の立て方は、一度で覚えることはできません。
最初のうちは気にすることなく、何度も繰り返して体で所作を覚えるように心がけましょう。

茶道のお稽古は、「お茶をいただく」「お茶を点てる」だけではありません。準備や後片付けも含めて、お客様をもてなす全てのことが茶道となります。
また、茶道には「歴史」や「茶道具」などの奥深い楽しさもあります。
茶菓子や懐石料理も楽しいですし、無限に茶道の世界は広がっていきます。