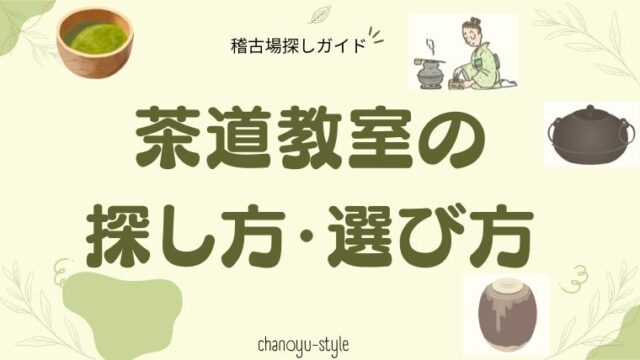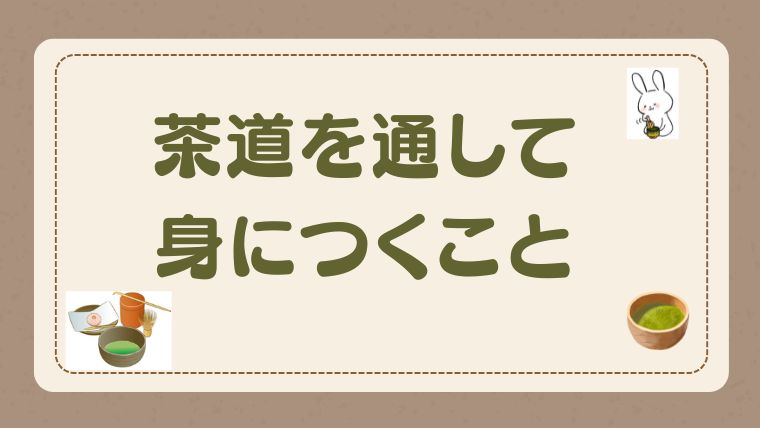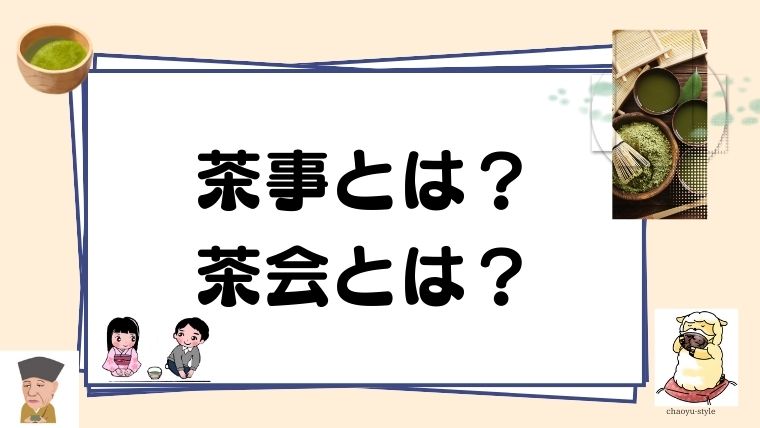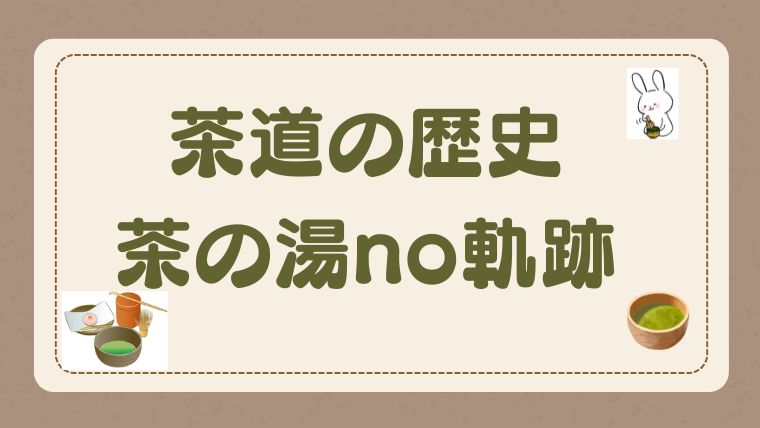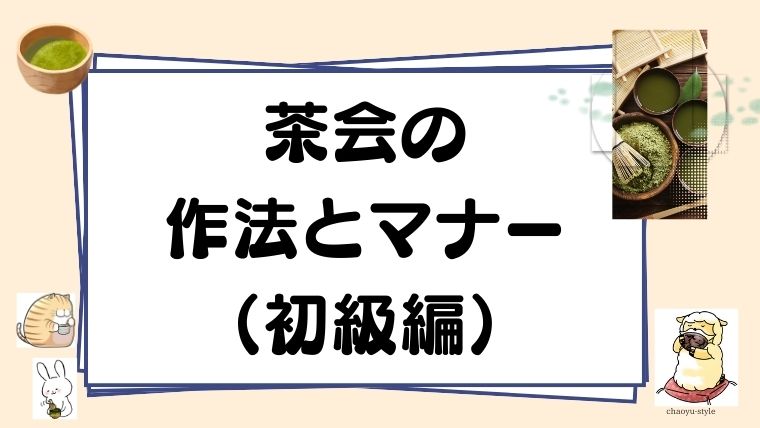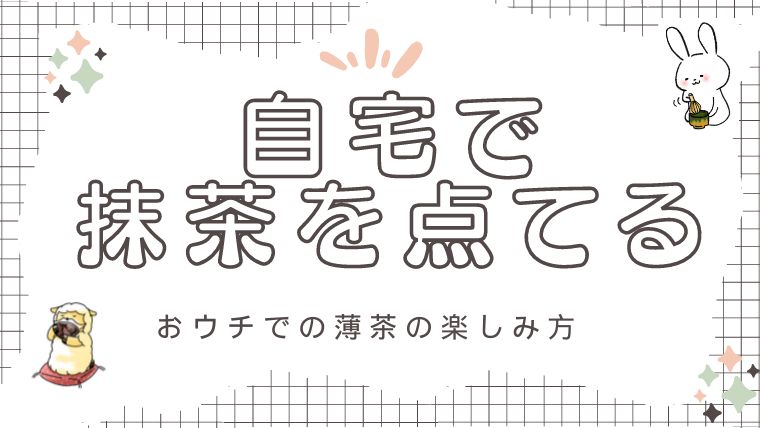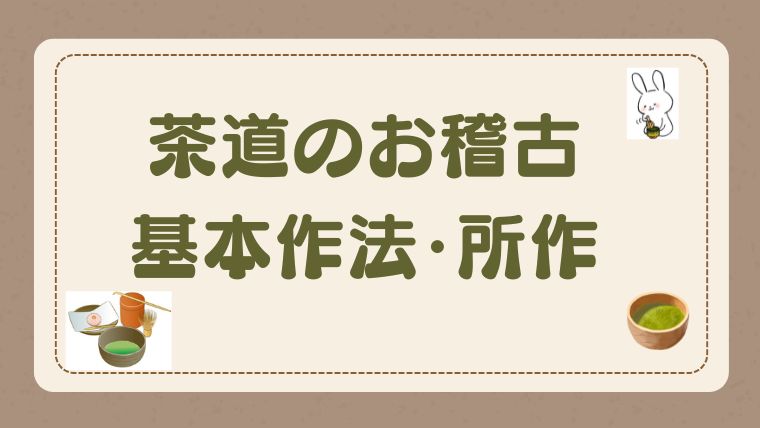茶道の心・精神を学ぶ→和敬清寂(四規)と利休七則(おもてなしの心得)
茶道を始めるにあたり、
知っておかなくてはいけない精神・心構えを確認したいと思います。

茶道の精神は素晴らしものがあります。
茶道の精神:和敬清寂
茶道で一番大切にしなければいけない心・精神はなんでしょう?
茶道には「千利休」が唱えた「和敬清寂(わけいせいじゃく)」と言う精神があります。
和敬清寂は、
茶道の精神性を表した四つの言葉であり、この四文字に茶道の心が凝縮されているのです。
和敬清寂について、順番にみていきましょう。
和 – 調和の心
「和」とは、互いに仲良くすると言うことです。
茶道では、亭主と客様は、互いに調和を保ち、心地よい雰囲気を保つことが大切とされています。
かの聖徳太子も「十七条の憲法」の冒頭に「和を以て尊しとなす」と唱えており、人間社会における基本精神と言えるでしょう。
敬 – 敬意の心
敬とは、互いに敬い合う心で接することです。
茶道では、自然、道具、亭主と客に対して深い敬意の心を持つことが重視されます。
人は1人で生きていくことはできず、互いに支え合うことで自分が生かされています。
清- 清める心
清とは、自分自身の心の汚れや、くもった気持ちの汚れを取り除くことです。
茶道では、心身と気持ちを清める素直な心を持つことが求められます。
寂- 静寂の心
寂とは、どのような事態に直面しても動じないことです。
どんな時でも動じないだけの心のゆとりを持つように心がけなければなりません。
後になってから後悔しないように、また失敗しないように、
あらかじめ準備を入念にしておくことが大切とされます。
事前準備をして心を作ってあることが重要なのです。
茶道の精神:和敬清寂
この和敬清寂の精神は、茶道の根底にある重要な思想です。
茶道の心得として大切にされており、茶道を学ぶ上で、この四つの心得を身につけることが求められます。
亭主側で客をもてなすとき、客として招かれたときに、
和敬清寂の精神を実践しようとする心構えを持つことが重要です。

和敬清寂の他にも、茶道には「利休七則」と言う心得があります。
利休七則について、以下で見ていきましょう。
利休七則
利休七則は、茶道における最も基本的な教え(精神)です。
頭では分かっている当たり前のことでも、
いざ実際に行ってみると、実践することは難しいものです。
物事をただ表面的に理解するだけでは何の役にも立ちません。
表面的な意味を理解するにとどまらず、
もっと深く理解し、常に実践することを心がけなくてはいけません。
千利休について、以下のような逸話があります。

茶の湯で心得ておくべき大事なものはなんですか?
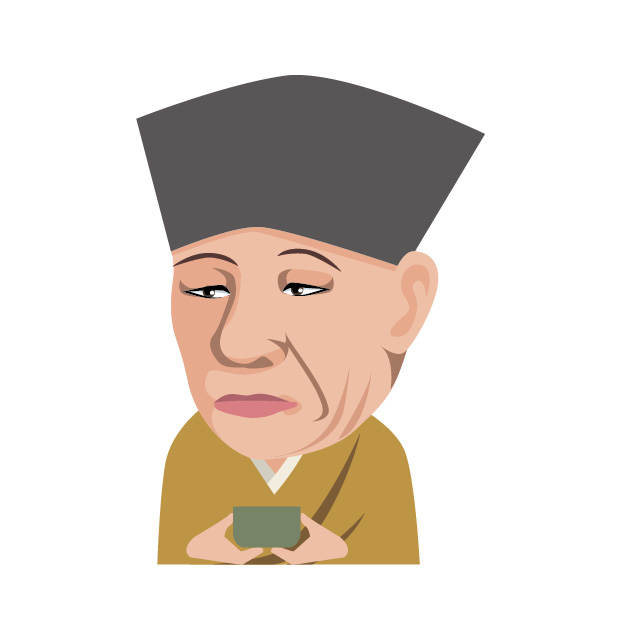
①茶は服のよきように点て、
②炭は湯の湧くように置き、
③花は野にあるように、
④夏は涼しく冬は暖かに、
⑤刻限は早めに、
⑥降らずとも雨の用意、
⑦相客に心せよ

それくらいのことなら私も知っています
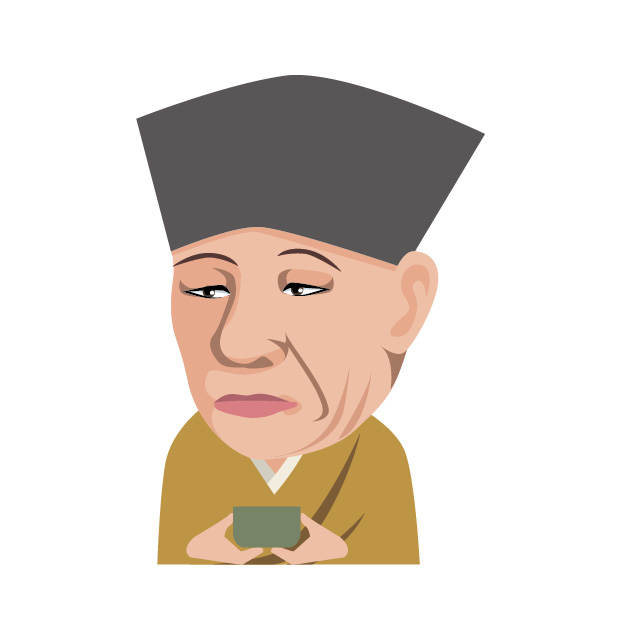
そうですか。では本当に、
もしこれができるならば、私はあなたの弟子になりましょう
①茶は服のよきように点て―心をこめる―
この利休七則は、
「お茶は心をこめて、飲んで美味しいように点てましょう」という意味です。
美味しいと舌で感じるだけではありません。
決して高いお茶という意味ではなく、
精神的な意味において、亭主と客は、心と心で通じ合うことが大切だと、千利休は教えてくれています。
亭主が心を込めて準備し点てたお茶を、客は感謝し味わっていただく。亭主と客が一体感の心を持つことを意味しています。
②炭すみは湯の沸わくように置き
炭は、単に火をつければ必ずお湯が沸くわけではありません。
しかも茶室においては、予定した時間通りに湯が沸くよう火を起こさなくてはいけません。
炭の置き方が悪いと、火は消えてしまうし、火が起こるまでの時間も変わってきます。
炭に関する知識・技術を指すのではなく、客に対して真心を込めましょう、ということに意味があります。
炭は、火の勢いが廻りやすいように酸素を取り入れる空間を作っておく必要があります。
ちなみに、その目的に叶うように炭を入れるのが「炭点前」です。
③花は野にあるように
自然に生える花こそが美しく尊いということですが、
千利休は「自然そのままに」花入れに行けるのではなく、
一輪りんの花に、野に咲く花の美しさに、花の命の尊さを生かす工夫をすることにこそ真の意味があると教えてくれています。
④夏は涼しく、冬は暖かに ―季節感をもつ―
茶道では季節感が大事にされています。
夏の暑い時期には、亭主はお客様を茶事に迎えるにあたって、
席入り時刻を早くする「朝茶事」を開催し朝の涼しさを味わったり、路地に打ち水をしたり、涼しげなお茶菓子を出したり、床に「涼一味」などのことばを掛けたりします。
一方、冬であれば、
炉を切って墨を炊いたり、温かい茶菓子を出すなどして、相手を慮る工夫をします。
⑤刻限は早めに ―心にゆとりを持つ―
刻限は早めにとは、「時間はゆとりを持って早めに行動する」ということです。
何事も早めに準備し対応しなくてはなりません。
ゆとりを持つことは、自分の時間だけでなく相手の時間を尊重することにも繋がります。
たとえわずかな時間であっても、相手の貴重な時間を奪うことがあってはなりません。無駄を省き、時間を大切にするように心がけましょう
⑥降らずとも雨の用意
どんなシチュエーションでも慌てることなく冷静な行動ができるように、
心の準備と物理的な用意をしておくことはとても重要です。
この利休七則も、茶人が心得るべき大切な心がけを指しています
どんなときでも「落ち着いて適切な行動」することの重要性を教えてくれています。
⑦相客に心せよ
「相客」というのは、同じく客の立場にある人を指します。
正客の座に座る人も、末客にいる人も、
互いにを尊重しあい、楽しい時間を過ごすことの大切さを教えてくれてます。
茶道では、お互いに労わり合い、一人一人が支え合う気持ちが大切です。可能な限り周囲の人に心を意識を持ちましょう。
茶道においては、例えば茶席でも
「お先に」
「お相伴(しょうばん)致します」
「どうぞ」
「いただきます」
「もう一服いかがですか」
という相手への労りの言葉がかけれています。
わび
後のわび茶につながる「草庵茶」という茶の湯を始めた村田珠光(むらたしゅこう)から始めり、
侘び茶を完成させた千利休の師である武野紹鴎は、
「正直で慎み深く、おごらぬさま」
を「わび」と表現しています。
武野紹鴎は、室町時代に流行した豪華・華麗な書院茶に対し,和敬清寂でも表現される簡素な趣や年月を経た風情や寂しさを美しいと感じる心がわびであると考えたようです。
一方、
千利休の考える「わび」は、自身の師である武野紹鴎が考える「わび」とはその内容が異なりました。
「新しいものをつくりだす生命力」
千利休はこれを「わび」と考えていたようです。
武野紹鴎は紅葉が過ぎた秋の夕暮れ時に「わび」があると考えたのに対し、千利休は冬の終わりから春を迎える頃に「わび」があると言っています。
白一面の銀世界の下で、わずかに発芽を始めた草木の、春の訪れを予兆させるようなところに「わび」があると言っています。
利休道歌
「利休道歌(りきゅうどうか)」は、「利休百首」とも言います。
これは千利休の教えを初心者にもわかりやすいよう、和歌の形にしたものを言います。
裏千家十一代の玄々斎宗室(げんげんさいそうしつ)が、茶道の心得や点前作法を三十一文字にまとめて百首集めたものです。

以下において、利休道歌をいくつか見ておきましょう
その道に入らんと思ふう心こそ、我身わがみながらの師匠なりけれ
この歌は、利休道歌のはじめに詠まれており、茶道を学ぶ者の心構えを説いています。
茶の湯に限らず、人がある道に入り学ぶ決意をしたならば、
学ぶ気持ちをしっかり持つことが大切であり、その学ぼうとする心こそが師匠であることを示しています。
茶の湯とはただ湯をわかし茶を点たててのむばかりなることと知るべし
この歌は、茶の湯は決して難むずかしいものではなく、お湯を沸かしてお茶を点て、お客様に差しあげ、そして自分もいただくという、日常生活にあることを示しています。
茶の湯のことを口で説明することができても、
実際にやってみると難しいということを教えてくれています。
千利休は、ただ湯を沸かして茶を点てて飲むことの難しさと大切さを教えてくれているのです。
稽古とは一より習い十を知り、十よりかえるもとのその一
習い事を初めルト、一から始めて次から次へと学びを進めていきます。
そして十に到達してもまた元の位置に戻って、再び一を習い、繰り返しながら茶道の到達点へ進みます。
どんなに修練を重ねても、繰り返し繰り返し基本に戻って、稽古を重ねることの重要さを教えてくれています。
はぢをすて(恥を捨て)人に物とひ習ふべし是ぞ上手の基なりける
知らないことがあることは決して恥ずかしいことではありません。
しかし、知らないことや分からないことを放置しておくことや、知ったかぶりすることは恥ずかしいことです。
素直に分からないことは人に質問して、教えを乞い、物事の本質を見極めることこそが、その道を極める秘訣だと教えてくれています。